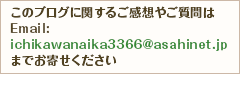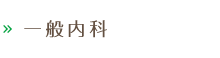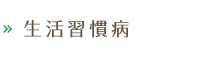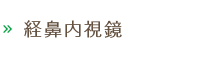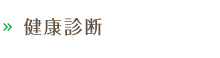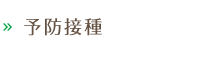私の本の読み方 30. 「病気であって 病気じゃない」
2024年9月21日
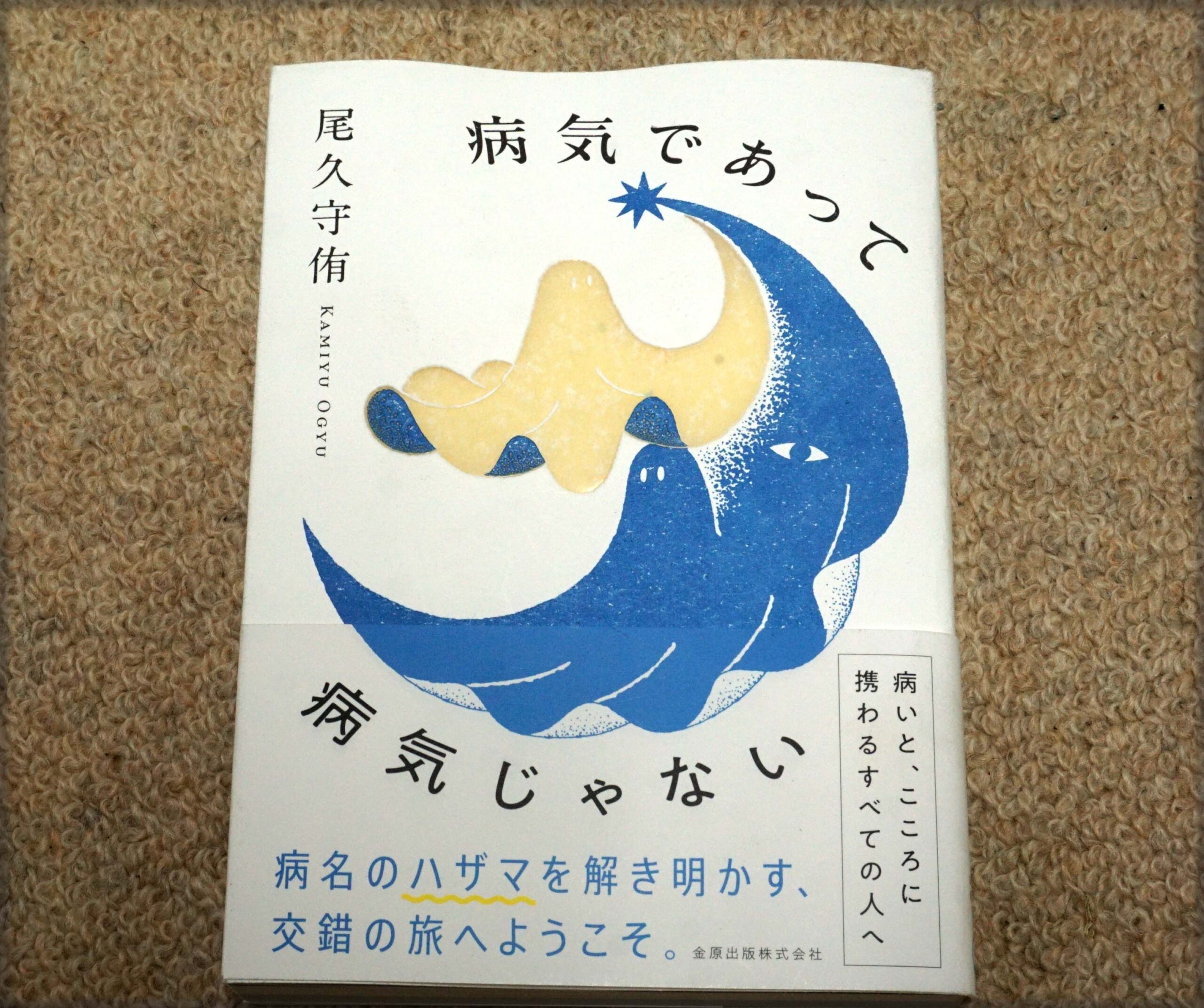
「病気であって 病気じゃない」 尾久守侑著 ☆☆☆ B6班で 200Pほどのソフトカバーですが、3,300円もしました。出版社を見たら主に医学書を出版する「金原出版」でした。高い買い物だったので、医学書と弁(わきま)えて読んでみました。(朝日新聞の書評は画家の横尾忠則さんが書いておられます) この本の対象は精神科の後期研修医向けだそうですが、いちぶ内科系の医師も対象にしているそうです。ただ、この本の後半部は(著者のフィクションではあるが)個別の症例と診断が書いてあって、一般者がその記述を自分の症状に当てはめて、自己診断するのは良くないことだと思いました。(患者自身が病気を診断するのに、自分の症状をあてはめ出すと、皆あてはまってしまうからです)
内容はごくかいつまんで話せば、「医者は外来患者を診るとき、病気か病気ではないか、単純に白黒をつけて診たがるが、病気はそのような単純なものではない。外来の患者を病気である部分と、病気ではないが患者の訴えを修飾する(外的な)部分とに分けて考えると、スッキリして診察しやすい」、みたいなことのようだ。私の読解力がないのでうまく説明できないが、物事は全て「ある」「なし」に区分するのではなく、現象を分けて考えることが大切らしい。
私の診察を反省すれば、「病気じゃないけど、病気である(訴えのある)」患者に、つい「異常ないから薬も出さない。あとは来なくて良い」と言ってしまいがちだが、これでは診察を受けに来てくれた患者の本意を汲んでいない。逆に、患者が何かの異常があって診察を受け来た時、医者が薬を出す際薬はあくまで補助的なものであることを丁寧に説明していると、「医者はつべこべ言わずに薬だけ出せばいいんだよ!」と言いたそうな患者がいる。あるいは「異常がない」と言って、その理由を丁寧に説明しても、「苦しんでいたので医者に来たのに、薬も出してくれない」とこぼす患者もいる。医者以外の読者も医療機関を受診する際は、医療者は何を考えて診察をしているか、そんなことを理解するためにもこの本が役立つかもしれない。