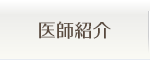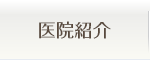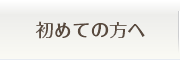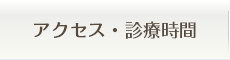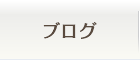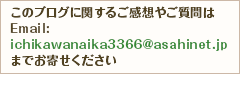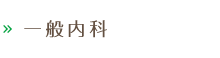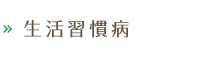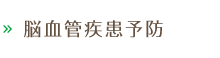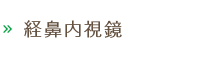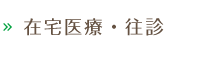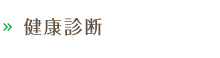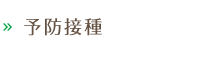311 アルコールに関する知識 3. 私が見た、聞いた日本酒醸造場
2025年11月11日
酒税は年単位で時々変更されるが、年度初め(4月1 日)から発効することが多い。学生時代、春休み(3月)に大きな醸造場でアルバイトした。4月1日の酒税増税の駆け込み出荷に備えて、瓶詰め作業が急がれたのだ。瓶詰めされた清酒はレッテルを貼られて、ベルトコンベアーに載せられて流れる。私はそのレッテルがきちんと貼られているかをチェックする係をやった。レッテル貼り機は時々不調になり、たまに貼られていない瓶が流れてくる。そんなときは不良品を刎(は)ねる。一つ不良品が出ると、続く瓶もずっと不良品が続くことがある。そんなときはラインを止める。瓶詰めを始めとするラインが全て止まるので、責任ある操作だ。何も起きないときはずっと起きない。たまに不良品が出るのをひたすら眺めていなければならない。たいていはアルバイトの仕事なのだが、この仕事は信用がない人には任せられない。そんな訳で私はその仕事を任せられた。不良品を取り出したり、ラインを止めたりするのは、迅速な行動が必要だった、
小学校の頃のある寒い冬の朝、造り酒屋の息子の従兄弟に誘われて、日本酒の仕込作業みを見学した。朝、暗い頃に造り酒屋についた。すでに蔵人たちは作業を始めていた。酒米は直径 3m もある蒸し器で蒸されていた。酒米は蒸し上がりのタイミングが重要である。それは蒸米で「捻(ひね)り餅」を作ることで始まる。杜氏の一人が、蒸米を30 cm 四方の板に乗せて、手首を反らせて手首の晩節で蒸米を練(ね)るのだ。出来た捻り餅を、杜氏の親方が押したり、ねじったり、齧(かじ)ったりして、蒸し上がりを判断する。OK が出れば仕込み作業が始まる。褌(ふんどし)一丁の蔵人が下駄みたいのを履いて蒸器の中に入り、木のスコップで蔵人が持つ桶の中に蒸米を入れていく。蔵人は蒸米が冷えないうちに醸造タンクに放り込む。一連の作業が終わって、私達は蔵人と一緒に、ワカメの味噌汁と野沢菜漬けだけの質素な朝食を食べた。
酒蔵にはよく入れてもらった、醸造中の撹拌作業や、酒搾りも見せてもらった。蔵には太いホースがポンプや搾り器やろ過器で繋がっていて、機械好きの私は興味が尽きなかった。搾りは「船」と呼ばれる大きな枡(ます)で搾る。醪(もろみ)の入った麻袋を積み重ねると、船に取り付けられた樋から濁った酒が出てくる。最後に酒袋に力を加えて搾りおえる、樋から出た濁り酒は、濾過されて清酒に変わる。
造り酒屋の娘だった母からは、酒造りの話を聞いた。 傑作だったのは、捻り餅を作りたがった小僧の話・・・ 新入りの小僧が、捻り餅を齧っている親方に尋ねた。「オレにも捻り餅を作らせて欲しい」 親方が言った。「捻り餅を作るには機械がいるから、街の造り酒屋から借りてこい」 街の酒屋で小僧が「捻り餅を作る機械を貸して欲しい」と言った。 街の酒屋の蔵人「ははーん、この小僧からかわれているな?」 家を持ち上げるときに使う重さ20kg もあるジャッキを持ってきて、「これだよ!」 騙された小僧はジャッキを荷車に乗せて持ち帰った。帰着して騙されてと知り、仲間に大笑いされた・・・そうだ。どこの酒蔵でもある都市伝説だろうが、昔の造り酒屋の風景だ。
もう一つ、母の話。 吟醸酒をもらって飲んだら、フルーツの香りがした。母は「昔はそういう酒を、メロン香がすると言って珍重したものだよ」と話した。今はセオリーさえ守ればどの酒蔵で吟醸酒や大吟醸酒はできる時代だ。 清酒、濁り酒、本醸造、純米酒、吟醸酒、大吟醸酒など、酒の種類、原料、製法は Web. に細く書いてあるので、興味のある人は調べてみて下さい。