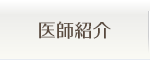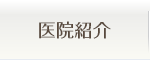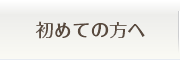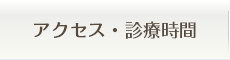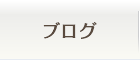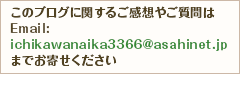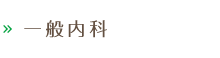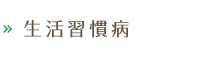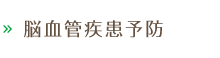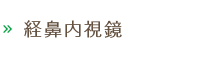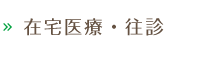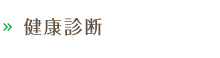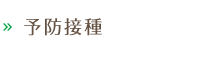アルコールに関する知識 1. 日本酒
2025年11月9日
ブログ実験室で新たなカテゴリー「アルコール」を設けました。私も勉強しながらお酒を論じます。
最初は日本酒です。日本酒は、糖化とアルコール発酵を一つの桶やタンクで同時に作用させる、世界的にも珍しい製法です。お米にアルコール酵母を直接作用させてもアルコールは生成されません。酒造りの最初は、米を麹(こうじ)酵母あるいは麹黴(こうじかび)または麹菌で糖に変えることです。(黴(かび)も酵母も菌も同じで、呼び名が違うだけです) できた糖にアルコール酵母が作用してアルコールが生成されます。これはアルコール発酵です。
麹は麴室(こうじむろ)呼ばれる温室のなかで作られます。蒸米に麹菌を作用させます。麹菌のアミラーゼは温度が低いと作用が鈍ります。(家で甘酒を作るときも炬燵の中で作りますよね) 糖化がある程度進んだら、コメ麹に水とアルコール酵母を加えて発酵過程をスタートさせます。ここまでは小さな容器(桶)で行われます。ここまでの過程で出来たものは醪(もろみ)の元です。さらに、大きなタンクに蒸米と元の醪を加えて、酒造りが始まります。
発酵の過程で、醪から炭酸ガスと熱が発生します。日本酒造りでは醪の表面に炭酸ガスの泡がブツブツと沸き上がり、同時に発熱します。発酵が進みすぎると、できたアルコールは酢に変わってしまうので、この過程までで、酢酸産生酵母を混入させないために、厳重な防菌作業が必要です。また、醪は高温では酢酸に発行するので、温度上昇を抑えるため、定期的に攪拌(かくはん)します。また、高温下では酒が酸っぱくなる、腐造、あるいは酸廃を起こしやすいので、昔(今でも)は、寒い冬の時期に酒造されました。
日本酒製造の過程で澱粉を糖に変えるのは麹菌ですが、ビール製造では麦芽に含まれるアミラーゼがその役を担います。ただビールは日本酒製造と異なり、麦芽の糖化は、澱粉の糖化が進んだ時点で火を入れてしまうため、それ以上糖は増えません。アルコール発酵は糖がなくなった時点で終了します。発酵の際発生する炭酸ガスを封じ込めるので、ビールは泡が出ます。ワインはブドウが最初から甘い糖ですから、アミラーゼは不要です。泡は日本酒とワイン醸造では炭酸ガスは大気に逃がしてしまいます。昔のどぶろくはご飯をよくかんで、唾液中のアミラーゼで糖化して、それを放置して自然界のアルコール酵母が作用させて造ったそうです。(雑菌が増えてたいていは失敗したそうです) ブドウを絞って瓶の中に入れておくと、自然界のアルコール酵母が作用して濃度の低いワインになります。炭酸が舌にピリッときて美味しいブドウのどぶろくですが、この程度は酒造法に引っ掛かりません。
麦酒やワインではアルコール発酵の過程で、原料の糖が使われてしまえばアルコール発酵は止まってしまいます。それに対して、日本酒醸造では、同じタンク(桶)の中で麹菌による糖化とアルコール発酵が同時に行われるため、糖は常に補給されていてアルコール濃度は上がります。最終的なアルコール濃度は、ビールで5度、ワインで10度で止まってしまいますが、日本酒は20度に及びます。因みに、アルコール濃度は、一般的には容量%で示されますが、化学(科学)の世界では重量%です。アルコール(エタノール)の密度は、0.79 g/ml ですから、アルコール度数はアルコール%の 1.27 倍です。