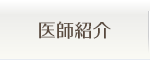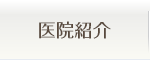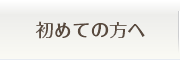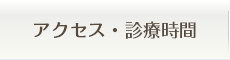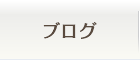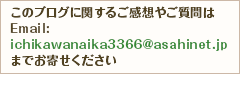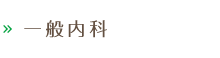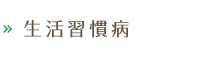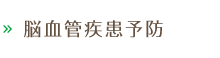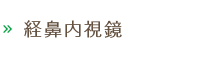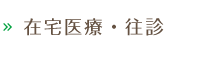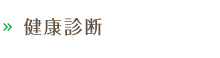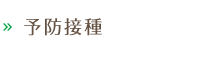310 アルコールに関する知識 3. 私が見た、聞いた日本酒醸造場
2025年11月11日
酒税は時々変更されるが、年度初め(4月1 日)から発効することが多い。学生時代、春休み(3月)に大きな醸造場でアルバイトした。4月1日の酒税増税の駆け込み出荷に備えて、瓶詰め作業が急がれたのだ。瓶詰めされた清酒はレッテルを貼られて、ベルトコンベアーに載せられて流れてくる。私はそのレッテルがきちんと貼られているかをチェックする係だ。レッテル貼り機は時々不調になり、たまに貼られていない瓶が流れてくる。そんなときは不良品を刎ねる。一つ不良品が出ると、続く瓶もずっと不良品が続くことがある。そんなときはラインを止める。瓶詰めを始めとするラインが全て止まるので、責任ある操作だ。何も起きないときはずっと起きない。たまに不良品が出るのをひたすら眺めていなければならない。たいていアルバイトの仕事なのだが、この仕事は信用がない人には任せられない。そんな訳で、その仕事を任せられた。不良品を取り出したり、ラインを止めたりするのは、迅速な行動が必要だった、
小学校の頃、冬に日本酒の仕込みを見学した。朝、暗い頃に造り酒屋についた。すでに蔵人は作業を始めていた。酒米は直径 4m もある蒸し器で蒸されていた。蒸米は仕込みのタイミングが重要である。それは蒸米を「捻(ひね)り餅」を作ることで始まる。杜氏一人が、蒸米を30 cm 四方の板に乗せて、手首を反らせて手首の晩節で蒸米を練るのだ。出来た捻り餅を杜氏の親方が押したりねじったりして、蒸し上がりを判断する。OK が出れ場仕込み作業が始まる。