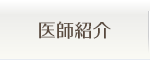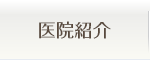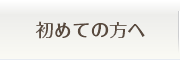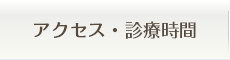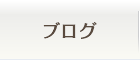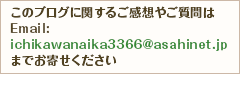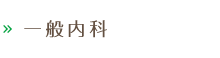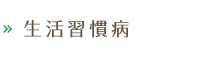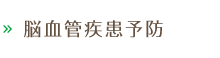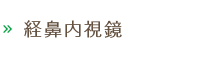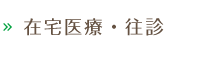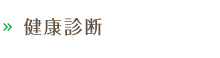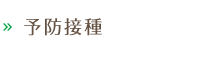箱山登山口の植物
2024年6月10日

相変わらず山菜あさりに嵌っています。まずキク科から・・・
1. ハルジオンの根生葉(ロゼット)です。春先に咲いた花の種がこぼれて、もう芽生えたらしいです。もともと、日本にはない植物なので、季節感がめちゃくちゃです。ロゼットも食べると美味しいです。
2. アザミだかノゲシだか花が咲かないと分からないけど、キク科だから・・・と、採ってきて食べました。他のキク科と混ぜて茹でたので、味は分かりません。
3. キク科のオオブタクサです。遂にこんなものまで、私の胃袋に収まってしまいました。手に触った感じはざらざらして不味そうだったけど、食べてみたら矢張りコソっぽかったです。でもとても柔らかくて味も悪くないので、葉を取って茎だけ煮付けたら意外といけました。 ブタクサの花粉は目や鼻の粘膜がターゲットで、IgAが関与します。誤って消化管に入ってもアナフィラキシーショックを起こさないと思います。だから、ブタクサ花粉症の人でも食べても大丈夫だと思うのだけれど・・、確信持てません。念のため、ブタクサにアレルギーのある人は止めておいてください。(もっとも、ブタクサなんてわざわざ食べる人は私以外にいないよなあ!) キク科でもブタクサは風媒花で花粉症を起こします。虫媒花の花粉は風で飛ばないから、ブタクサ以外は花粉症は出ないです。
4. いつの間にかヒメジョオンの咲く季節になっていました。こんなにけなげに咲いているのに、「雑草だ!」とヒトに毛嫌いされて可哀そうです。どうか皆さま、食べてやって下さい。

5. 今年のウツギの花付きはものすごいね。温暖化の影響でしょうか?
6. 去年は少なかったけど、 今年の柿の実の付きはまずまずです。去年は柿の花の時期に遅霜があったそうです。ところで、全国的に今年の梅の実の付き具合は異常に少ないです。バラ科の果物は冬にある程度の低温の日がないと咲きません。例えば、サクランボは気温7℃以下で積算時間が 1,400時間以上になると開花のスィッチが入ります。そのあと気温が上がるとか、ハウス内で加温すると蕾が膨らむのです。今冬は暖冬で、開花のスィッチが入らない前に気温が上がってしまって、そのため花のつき方が悪いのです。TVで「今年は梅が不作だ」とは言いいますが、このメカニズムを説明した報道は見かけません。 ところで、サクランボの花の花粉症は一般的にはありませんが、人工授粉をする人の中で、バラ科(とカバノキ科)にアレルギーがある人は、作業中に花粉症が発症します。乾燥した大量の花粉が目や鼻に入るからです。バラ科の植物は虫媒花が多いので、花粉症は稀です。花が良い香りがするとか、きれいに咲く、等々は花が虫たちを誘う花は皆虫媒花です。
7.マタタビ 疲れて宿に辿り着いた旅人が、マタタビの実の塩漬けを食べて元気を取り戻して、翌日、「また旅」に出かけたとか・・・・。 マタタビが咲く頃、一部の葉先が白変します。
8. マタタビの葉裏にひっそりと花が付いています。マタタビの花はちょうど梅雨の時期に開花します。花は雨に弱いので、葉っぱの傘の下で咲きます。花が咲く頃に、虫たちに良く分かるように葉先が白くなり、花は芳香がします。「花が咲いたよ」と虫たちに教えているのです。丁度、「新蕎麦出来ました」と旗をかかげたり、「ウナギ焼いています」と団扇で扇いで臭いを送るのと同じです。
マタタビはマタタビ科の樹木です。サルナシ、キーウィフルーツが同じ仲間です。(因みに、キーウィフルーツは、中国のサルナシがニュージーランドで品種改良され、できた果実がニュージーランドにいるキーウィ鳥に似ているから、こう名付けられました) マタタビ科の果実に、ネコ科の動物は反応します。キーウィフルーツの幹にネコは体をこすりつけて喜ぶそうです。 マタタビの実を焼くと、煙に誘われてネコがやってきて、ごろごろ寝転がって恍惚状態になります。ネコ科の動物全41種は皆マタタビに反応します。ライオン、トラ、ヒョウ、チータ、ピューマ、ヤマネコ・・・。 ところで、お宅のネコはキーウィフルーツに反応しますか? 教えてください。
マタタビ科の果実の種子は哺乳類の消化管を通過して、発芽OK状態になります。サルナシはサルに好かれるような味があり、サルが好んで食べるので、サルナシです。 マタタビもネコに好かれる様な成分が入っているのかも知れません。近年サルが増えてきて、鴨ヶ岳ではこれまで生えていなかったサルナシを見かけるようになりました。同じころから、山の中でキーウィフルーツの木を見かけます。サルが里に出てきてキーウィフルーツを食べ、山の中糞をして種子は発芽する・・・、と言うメカニズムです。種子を包んでいるペクチン質が、動物の消化管を通過中に溶けて、種子が裸になって発芽OK 状態になります。種子が動物たちに運ばれて遠くまで運ばれる仕組みです。ヤドリギ、ナナカマドの種子と鳥類の関係と同じです。