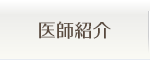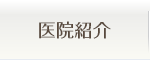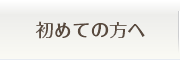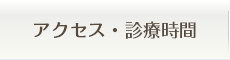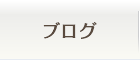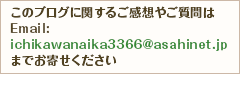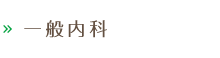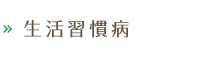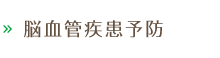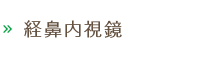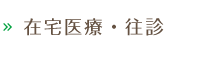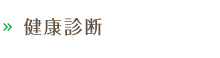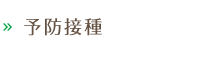2563 ハナカタバミの花
2025年10月16日

医院の花壇で毎年咲きます。別に植えた記憶はないのですが、近くにこの花を植えたフラワー・ポットを置いた記憶があります。種がこぼれて根付いたのでしょう。
ハナカタバミは南アフリカ原産のカタバミ科の草本です。日本には黄色い花のカタバミが自生しています。カタバミの特徴は、種子がこぼれる時に遠くに飛び散ることです。種子が成熟すると、蒴果はいつ裂開しても良い状態になります。軽く触れるだけで蒴果は弾けて、内部の種子が勢いよく飛び出します。種子は小さいけれど硬いので遠くまで飛びます。不用意に顔を近づけると、蒴果に触れただけで種子が弾け飛ぶので、顔にパチパチ当たります。目に入ると厄介です。
このように種が弾け飛ぶ草本に、ゲンノショウコ、ホウセンカがあります。これらの植物はひとたび芽生えると、辺り一面に繁茂するので厄介です。
カタバミの葉はシュウ酸が含まれるので、齧ると酸っぱいです。むかしから刺身のツマに使われました。(シュウ酸は尿酸結石を起こす恐れがあるので、摂り過ぎには気をつけて下さい。) 以下落語「カタバミ」の話です。熊さんの家の庭にはカタバミが生えています。八っつあんが、「刺身が手に入ったので、カタバミをお呉れ」。クマさん「いいよ」。翌日も、八っつあん「カタバミを頂戴」、クマさん「いいよ」。それが毎日続くので、クマさん「カタバミがたくさん手に入ったから、刺身を頂戴」、八っつあん「・・・・・」。
ハナカタバミは増えすぎて厄介だけれどきれいです。野生化しているのを見かけます。