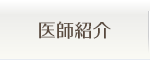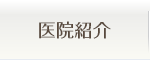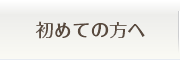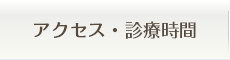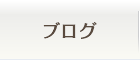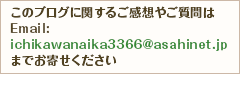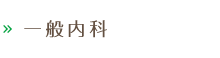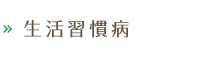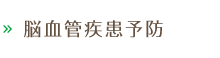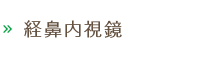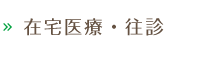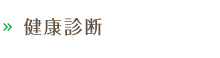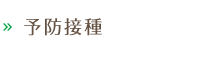鴨ヶ岳の植物
2023年3月31日

日当たりのよい斜面で、イカリソウが「今年もよろしく」と挨拶してくれました。花の名の所以(ゆえん)は船の錨(いかり)です。ところで、私は最近鴨ヶ岳か箱山のどちらかに登る様にしています。箱山登山道は北向きなので、半日陰で湿りけが多く、寒地性の植物が多いです。引きかえ鴨ヶ岳登山道は南西に面し、乾燥しています。環境の違いで両者の植物相には差異が多いです。ここでは鴨ヶ岳の植物を紹介します。

ホソバカンスゲ です。カンスゲより葉の幅が狭く、日本海側に多生します。4日前に真っ白な花が咲いていてきれいだったので、この日カメラを持って登ったのですが、花は黄色っぽくなっていました。しかし花は今が盛りのようで、指ではじいたら花粉が勢いよく飛び出しました。

スミレの同定は難しくて、私には良く分かりません。一応、タチツボスミレとしておきます。

オクチョウジザクラです。チョウジザクラは萼筒に細い毛が多生しますが、オクチョウジザクラは毛が少なく、つるつるしています。山では春一番に咲くサクラです。

ウグイスカグラの花です。夏には赤い果実が熟します。

シシガシラの去年の栄養葉(緑色)と胞子葉(茶色)です。地面が落ち葉で覆われるこの時期、緑の葉が目を引きます。

キブシの花です。キブシの「ブシ(五倍子)」は「ゴバイシ」とも読みます。五倍子は鉄漿(おはぐろ)の原料になる植物の総称で、一般的にはヌルデの葉にできる虫えい(虫こぶ)を指します。虫えいにはタンニン酸が含まれ、鉄釘などの鉄分と結びついて黒色の鉄漿になります。キブシの果実にもタンニン酸が含まれ、五倍子の代用になります。
ブシという言葉は、附子のことも指します。トリカブトの根を漢方では附子と呼び、補陽、温裏、止痛の効ありとされます。